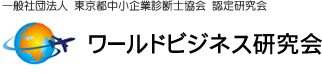民主主義発祥の地にして、ヨーロッパ文明のゆりかごと言ってもよいギリシャは、美しいエーゲ海の島々の景色も楽しめ、物価も西欧に比べると比較的安いとあって、特に夏のバカンスのシーズンには世界中から多くの観光客が訪れます。西や北ヨーロッパの人々は、東京の人間が沖縄へ行くような感覚でこのエーゲ海を含む地中海へ繰り出しますから、国家としての観光産業の位置づけも今の日本のそれを上回ると言って良いでしょう。

そんなギリシャで遭遇しました、ストライキ。なんと国のシンボルと言ってもいいほどのあのパルテノン神殿がストライキとのこと!ホテルでもアテネ市内界隈でもそんな情報には触れられなかったのですが、アクロポリスの丘を登って入口へ向かう途中、どうも上から降りてくる人が不自然に多いため観光客風の人に試しに声をかけてみると、「今日はストライキだって!」とのことでした。せっかく両親を連れて行ったのですが、二人には人生最初でおそらく最後のギリシャ観光もハイライトではしごを外される格好になってしまいました。
私が不自然に思うほどに丘を降りてくる人が多かったところをみると、断定はできませんが、事前に、あるいはアテネ市内において、あまり観光客に周知されている感じではなかったような気がします。また、ストライキ自体が本当に急遽決まったという可能性もあるでしょう。東京に例えれば浅草寺とスカイツリーが同時閉鎖になったようなもの(おそらくそれ以上のインパクト)かと思いますから、そもそも日本ではまず考えられない事態ですし、もう少し外国人観光客への配慮があっても良いように思います。あるいは、ストライキというものがかように珍しくないのかもしれません。おそらく、やや後者寄りでしょう。
ギリシャのストライキといえば、というよりストライキといえばギリシャを思い浮かべる人もいるかもしれません。2010年頃に世界を揺るがしたギリシャ危機によって、世界経済はハチの巣をつついたような大騒ぎになりました。同国の財政破綻が明るみに出てユーロやヨーロッパの国債が暴落、その波及で世界経済破綻が現実味を帯びるほどのインパクトでしたが、ギリシャ国内では恵まれた(危機の大きな原因である)立場の人たち(公務員、他)が自分たちの利権を守るためにストを連発、顰蹙(ひんしゅく)という言葉を使っていいほどの印象を持ったことを記憶しています。

あれを機にEUの相互関係がやや懐疑的な方向へ向かってしまったような印象を私はもっており(その後の移民問題でさらにダメ押しの感があります)、もしかしたら将来、「あれが転換点だった」というようなことにならなければ良いと思いますが、私がストライキに出くわしたのはこのギリシャ危機が落ち着いて5~6年も経った頃でしたけれど、ギリシャ国民も「もうストライキはやめよう」などとはあまり思っていないようです。
アテネの町中を歩いていて感じるのは、まず仕事をしていない人(特に中年男性、平日休みの人ももちろんいると思いますが)の多さ。ギリシャの失業率は危機の際には25%を超え、町中に失業者が溢れるのは致し方のないことですが、腑に落ちないのは割と余裕のある?失業生活を送っているように(全ての人ではないでしょうが)見える人も少なくないこと。真っ昼間から街中のレストランのテラス席でビールやワインを飲みながらチェスなどに興じている人があちこちにいます。新橋の赤ちょうちんで昼間から一献傾けながら碁を打っている失業者は・・・まずいないでしょう。

旅行者の天敵であるストライキには、他にもフランス、ベルギー、スペインなどで出くわすことが多いですが、ストライキの場面に限らずこの「余裕な感じ」はギリシャにいると他にも少なからず感じることがあります。
例えばギリシャ各地のお土産店などは好例かもしれませんが、世界的に著名な観光地があり、その国の経済の観光への依存が比較的大きく、その結果土産店の数も多いような国では一般的に店員の情熱はすさまじく、巣に掛かった観光客はクモの如くがんじがらめにして、少しでも高く、多く、購入を促そうとする傾向があります。その反対は反対で、土産物は多くもないし、しかも全て定価のような国では、店員の態度は非常に淡泊に見えることが多いです。
ギリシャは前者の条件を満たしながら、店員は概ね実に“紳士的”で、大体が「買いたければどうぞ」という雰囲気でしょうか。もちろん価格も良心的なため、価格交渉してまでという動機は店員と買い手相互に乏しいように思えます。カモが隣りのライバル店に逃げてしまっても、それはそれといった感じ。そして、隣りの店に行っても、3軒隣りに行っても同じものが同じ値段で売っています・・。
ただそれは、非常に買い物がしやすい国ということでもあり、不平どころか観光客からすると非常にありがたい話ではあるのですが。
さらに20年ほど前にさかのぼる頃にギリシャを訪れた際、非常にユニークな絵葉書があってとても気に入り、購入して大切にしておいたものがあったのですが、この時もまた同じものが店先で売られていたのを見つけた時には嬉しさ懐かしさとともに「マジか?!」という信じられない気持ちも大きかったことを覚えています(この時は私の母もこれを気に入り、購入しました)。

ギリシャではよくある風景
ギリシャの町中の人々から往々にして感じるものは、他者との経済競争に打ち勝って豪邸暮らしを目指すことでも、新しいビジネスや価値観、システムを創造して不断に社会を変革していこうという強烈な意志でもなく、今のまずまずの暮らしを大過なく全うできれば十分満足という気持ち、といったら言いすぎでしょうか。その気持ちが強ければ強いほど、その妨げとなる変革に対しては断固として立ち向かうという姿勢が、もしかしたら前述のストライキにも表れているのではないかと推測したら、これもまた考え過ぎでしょうか。
社会というものは有為無常で絶えず変化していくのが不可避なのであれば、新たなシステムや前例のない不確実な方法を考案して新しい時代に対応できるよう、制度や慣習を変革、改革していくことは社会を維持するのに一定程度必要ということになります。それを阻む要因が多い社会は動脈硬化を起こしやすく、それを過度に求める社会は、常に革命や騒乱などの社会不安に晒され続けることになります。
何千年もの昔に人類の普遍的価値を生み出したと言えるギリシャの人々が、もし今は本当に私の推測通りなのだとすれば、ちょっと残念な話ではあるのですが。

神々の前で議論を戦わせた。
中小企業診断士 中原健一郎