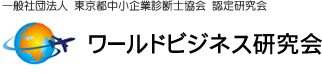時はまさに世紀末(大げさに言ってるだけです、笑)の2000年頃、東ヨーロッパを何か国か訪問しました。チェコのプラハに飛んだのですが、当時はインターネットが出現し始めていたものの、パソコンで航空券の予約などをするようになるのはもう少し後のことで、当時は日本の旅行代理店で買える割引国際線航空券は日本発の往復航空券のみでした。
海外発の航空券、特に片道というのは日本ではまず手に入らない時代で、どうしても必要な時は日本発の航空券手配をお願いした航空会社や代理店(日本航空やJTBなど)に電話で頼み込み、ノーマル運賃(例えば東アジアと欧米間ならエコノミー片道30~40万円ほど)を支払って、それでも発券してもらえるかどうかは不確実といった感じでした。この時はバンコクの旅行代理店の情報が雑誌に掲載されているのを見つけ(当時は情報がほしければまず書店からで、このような代理店の情報でさえも、超の付くレア情報でした)、FAXで連絡を取り、バンコク発プラハ行きの割引航空券を何とか手配してもらったのを懐かしく思い出します。
当時を書き留めておきたく冒頭から傍論になってしまいましたが、話はプラハを後にしてスロバキアの首都、ブラチスラバに入った時のことです。長距離列車でブラチスラバに着き、一息ついてから路面電車に乗車しました。

乗車したらまず切符(もちろん紙製)にパンチで刻印をするのですが、車内に据え付けてある刻印機の調子が悪かったようで、試行錯誤しながら5回も6回もトライしたのを覚えていますが、なかなか上手くいきません。そのうちイヤになって、完全に刻印はできていないものの、何度も刻印されようとした跡がくっきり切符上に残ったため、これでいいかと諦めて乗っていました。
その時、ヨーロッパではよくある話ですが、乗客の振りをして乗っていた検札員がスッと立ち上がって検札を始めました。ターゲットは完全に私でしょう。私の切符を見るなり、外に降りるよう指示してきました。
この検札員、実は刻印機のわりと近くに座ってずっと私の試行錯誤を見ていたはずの人なのです。それは本人達(2人組)も認めているのですが、
「私に不正乗車をするつもりがなかったのは見てて分かりましたよね」
「そもそもあの刻印機壊れてましたよね」
「1~2時間前に初めてスロバキアに着いたばかりで、勝手もなにも分からないんですが」
何を抗弁しても、そんなの関係ないと言わんばかりで、
「あなたは罰金を支払わなければならない」
「This is my job, sorry.」
を繰り返すばかりで取り付く島がありません。
初入国したばかりなのでスロバキア・コルナ(当時はまだユーロ未導入)をほとんど持っていない(本当に持っていませんでした)と言ってもだめで、それなら外貨で払えと言って全く譲る気配はありません。
すでに近くのビルの物陰のような所に連れて行かれてましたので、周囲の人の助けも期待できませんし、もはやこちらが折れるしかなく、少なからぬドルを持っていかれました。
別れ際の一言は、“Have a nice trip.”
あんたらに言われても全然嬉しくないわ・・・
今、日本にインバウンドが増えているのは既知の通りですが、仮に彼らが上記のスロバキアの話のような状況になった場合、日本の係官はどのような態度をとるでしょうか。恐らく、多少は融通を利かすのではないかと思います。
イタリアの駅にも刻印機が多くありますが、壊れていることも多く(イタリアらしい)、乗車後に自分から車掌に願い出て、悪意がないことを示せば「OK、OK」みたいな感じで理解してもらえたことも何度かありました。席の指定がされていないのに、全席指定のその号車に何となく居させてくれたインドの車掌もいました(そういう切符でもNo problemと言って窓口で売ってくれるインドの大らかさには逆に戸惑うことが時々ありますが)。こんな話は、数え上げればキリがないと思います。

(男性のすぐ左、柱に据え付けてある)。サレルノ駅にて
翻って、外国人観光客たちは、日本で上記のような状況になった場合、罰金を払うでしょうか。成田空港周辺で増加して問題になっている、いわゆる“白タク”の外国人運転手が、摘発に向かった警察官に対して「友達を迎えに来ただけ」と頑として抵抗している様子はネットやテレビでもよく見かけることがあります。
これらの背景には、社会における所謂「お上」の存在感、位置づけというものが大きく関係しているようにも思えます。基本的に公僕は市民への奉仕の形を取る日本のような国では、白タク運転手の言い訳はウソが大半でしょうけど、一応正当な抗弁として取り扱うことが順当な対応として不文律的に認識されていると思います。一方で不可抗力に近い形でも罰金と相なった私のスロバキアのケースからは、役人たちは権力を駆使して衆人を統治し、社会秩序を維持するのが使命であるという、非常にヒエラルキー的な社会・権力構造の断片を感じるところがあります。これはどちらが良い悪いとまで言うつもりはないのですが。。。
スロバキアの独立は1993年、チェコスロバキアが分離する形で誕生しました。それまでの約75年間、スロバキアは一つの国でありながら、「チェコ」というより大きな存在感の重しと共に国家を運営してきました。そして、そのチェコスロバキアの上にはソ連というさらに強大な重しが長い期間あったことも周知の通りです。そんなスロバキアが、周囲との階層的な関係性の中で「上には従う」という文化的傾向を持つようになったとしても、不思議ではないような気がします。
ホフステードの6次元モデルによれば、スロバキアは権力格差の項目において100点満点(もちろん世界一)を取得しており、こういったところにもこの国の権力への向き合い方が数字として表れてきているのだと思います。首都トラムの世界一融通のきかない検札員も、その権力格差の証左の一つではないかと感じるわけです。
中小企業診断士 中原健一郎