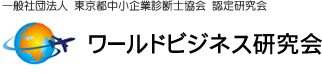<エピソード>
「中国人は4本足のものは机と椅子以外、2本足のものは家族以外、飛ぶものは飛行機以外、水中のものは潜水艦以外、なんでも食べる!」とよく言われる。多種多様な料理があるが、その中には「珍味」や「ゲテモノ」と呼ばれるものも含まれている。
私も1983年-1988年の香港、1994-1998年の上海、そして2001-2006年の香港および広東省に駐在の際に、中国大陸への出張時も含め、日本ではお目にかかれない料理を色々食したものである。
例えば、オオサンショウウオやアルマジロ。どちらも土鍋煮料理でコラーゲンたっぷりの美味であった。あるいはサソリ。これは唐揚げで大皿に山盛りで供され圧巻であったが、非常に危険な料理との印象が鮮明に残っている。毒はないのだが、棘が凄まじく、気を付けて食べないと口の中が血だらけ状態となる。
もちろん一般的な料理も非常に美味しい。下記は香港で80年以上続く人気老舗広東料理店「Yung Kee Restaurant(鏞記酒家)」における私の大好きなランチセット(「チャーシュー(叉焼)・ラプチョン(臘腸)・シューゴー(焼鴨)+ピータンの甘酢生姜添え(酸薑皮蛋)

<考察>
中国の食文化は、五千年にわたる歴史を背景に発展してきた。そのため、考察に当たっても様々な観点からの切り口が考えられるが、今回は人の置かれた立場という面からひも解いてみる。
中国の有名な詩人である杜甫の詩に「朱門酒肉臭、路有凍死骨」というものがある。
「赤い御門の富貴の者においては、酒や肉の贅を尽くして余ったものが腐敗臭をだしているが、そのそばの路傍には凍えて死んでいる人の骨が横たわっている」という意味である。
極端な言い方をすれば、中国の食文化は「グルメ」と言われる特権階級の文化から生まれた一方で、飢餓から生まれたという二つの側面があると考えられる。食べ物に対する強い執着をベースにした歴史的背景があるのではなかろうか。つまり、多くの庶民は食べられない時代が長かったことから、食べられるときに必死になって食べる。そして、食べられるときにより良いものを求めるということに執着し、そこに特権階級の文化が結びつき、更なる美食を求めた結果、「グルメ」としての中華料理に発展したとも言える。別な言い方をすれば、庶民は飢餓のために普通では食べないようなものも食物にせざるを得ず、これが「ゲテモノ」と称されるものとなる。一方で特権階級においては「ゲテモノ」のなかから美味なるものを選別の上、「グルメ」に発展させたと考えられる。
ところで、中国人の食に関する強い執着を皮肉ったジョークは沢山あるが、一例として下記をあげておく。
- 豪華客船の沈没に際し、救命ボートは定員オーバーで子供や女性を優先させるため、各国の男性には海に飛び込んでもらう必要がある。
・アメリカ人に対して:あなたが海に飛び込めば、あなたは真のヒーローになれる。
・イギリス人に対して:あなたが海に飛び込めば、あなたは正真正銘の紳士だ。
・ドイツ人に対して:あなたは海に飛び込まなければならない。なぜなら、それがルールだからである。
・日本人に対して:他の男性たちは既に海に飛び込んだよ。
・中国人に対して:海には美味しそうな魚がいっぱい泳いでいるよ。
- 料理店でビールを注文したらジョッキに蠅が一匹浮かんでいた。
・イギリス人:一言も発せず、黙ってお金を置き、ビールは飲まずに帰ってしまった。
・フランス人:店員を呼びつけ、さんざん文句を言って、蠅の入っていない新しいジョッキを持ってこさせた。
・ドイツ人:蠅を取り除き、「アルコールには消毒作用があるから問題なし」として、ビールを飲みほした。
・日本人:会社に電話をして、どうすべきかお伺いを立てた。
・中国人:「これは珍味だ!!」と嬉しそうに蠅をツマミにビールを堪能した。
<結論>
異文化理解を深めるためには、他文化の慣習や価値観に対して偏見を持たず、積極的に受け入れようとする姿勢が必要である。中国の食文化もその一つで、私たちが「ゲテモノ」として認識する食材も、その土地での歴史や習慣、気候に根ざしたものであるという観点から、単なる驚きや嫌悪感を呼び起こすものではなく、自分の常識を一歩引いて、他者の文化や価値観に対して柔軟な姿勢で接することが重要である。例えば<エピソード>冒頭の「オオサンショウウオ」や「アルマジロ」はコラーゲン、「サソリ」はカルシウムの摂取に役立っている。食べ物を通じて、他文化の違いを尊重し、学ぶことは、グローバルな社会に生きる私たちにとって欠かせないスキルとなること必須。次回、中国の料理を試す際には、その背後にある深い歴史と文化にも思いを馳せ、味わい・堪能されては如何?
中小企業診断士 山本倫寛